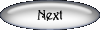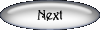我、妖怪に御座候
□午後七時十一分_罠の中
1ページ/1ページ
「また、夜。」
街灯の光を避けて、住宅の塀の前に立つ。
今までなら、僕に気づかないはず君が、振り返って微笑んだ。
「いつも夜ね。」
どこか危うい君の瞳。
酔っているわけではないのに、揺れているのはなぜか。
内心の動揺を隠して君の隣に立つと、見えたはずの翼を無視して微笑んでくれる。
『見えないモノは信じない。』
いつもそう口にする君が、『見えるモノ』を無視する異常さに知らずカラダが強張った。
「…どうして黙ってるの?」
気をつけたつもりでも、君に口づけた時に僕のチカラが流れてしまったんだろうか。
脳裏に浮かぶ可能性に、ないはずの心の臓が震える。
「翼、気にならない?」
訪ねた僕の声は緊張で掠れているのに、君は首を傾げて媚びるように僕の腕に手を絡ませた。
「どうして?」
面白いことなど何もないのに、クスクスと笑いしなだれかかる。
君であれば、するはずのない仕草に恐怖を覚えた。
何が起きてる?
胸の奥でなり始めた警報の意味を悟って、歩くのをやめた。
気を飛ばして君の気配を探す。
「誰だ。」
「あたしよ? わからないの?」
クスクスと笑い続ける外側だけ君のカタチの何かに、目を凝らした。
君と同じ顔の別の何かを見極めようとすると、薄っすらとかかる靄に阻まれ見えなくなる。
それでも…、そこにいるのは、君じゃない。
「誰だ。」
巻きついていた手を強く握り、逃がさないようにした。
君の気配が見つからない。
その焦りだけで、気が狂いそうだ。
この間、ちゃんと自覚したはずだった。
僕の存在が君にとってどれほど危険か。
何の準備もないままにしてはいけないとわかっていたはずだった。
驕り。
君は大丈夫だと。
僕が守ればいいと。
その結果がこれだ。
愚かな自分に腹が立つ。
「彼女は、…何処だ。」
認めたくない現実を、…受け入れた。
「彼女って誰かしら? 姥桜のキツネさん? それとも、一夜の情けさえ拒んだ姫のこと?」
微笑む何かは、君の姿で憎しみの目を向け僕を責めた。
「…一人だけ楽になろうとは、ずいぶんと虫のいい話だな。」
くっ、と笑いをこらえるような溜息のあと、異質な声が形のいい君の唇から零れた。
「お前。」
「ほう、わかるか?」
「…虚(ウツロ)。」
今まで忘れていた懐かしい名前を呼び、虚が前に別れた時と同じ目で僕を見ていることに気づいた。
名と同じように、ひかりを映さぬ黒い闇。
今は、そこに僕だけが映り、憎しみで光っている。
「何をした。」
出会いから…虚に疎まれていたのは知っている。
だから避けているというのに、虚は僕が彼を忘れた頃、現れては苛む。
それほどまでに憎まれるナニをしたのか。
わからなくても、君が何処にいるのか、きっと虚が知っている。
「なに、お前がそうまで大切に想うモノなら、挨拶くらいはせんとなぁ。」
君の姿のまま、憎悪を浮かべて嗤う虚から、目を逸らしたくなる。
「ほれ、そこにおろう? お前も堕ちたものだな。見えぬとは…。」
虚が指さす空中にわずかな空間の綻びを見つけた。
別の世界を作るのは、虚が得意とするところ。
裂け目の向こうに微かに君の気配を感じて、虚から離れた。
「そこな穴はじき閉じようぞ。我の世界は中のモノの生気を奪う…ヒトがいつまで耐えられるか、見ものよの。」
背中から聞こえる虚の声は、もう君を装うこともなく、彼本来の嘲りに満ちたものだった。
飛びつくように薄い切れ目に手をかけて、閉じようとする世界に飛び込んだ。
中は、薄闇に覆われた不透明な世界。
虚の気配に支配された世界は、僕のカラダからもチカラを奪う。
チカラだけでなくカタチさえ奪おうというのか、この中では自分の姿さえ曖昧で、一歩進む度、目の前の景色がねじれる。
森の中にいるようなのに、前に見えるのが何の樹なのか見分けがつかない。
音はすぐに吸い込まれ、どこを向いても見通せず、いくら歩いても進んだ気がしなかった。
どれほど歩いたのか、ようやく森を抜け、平地に来たと思えた頃、遠くに陽の赤い光が見えた。
朝が近づいてるのか?
時間の感覚さえ失い、靄に霞む赤い光が陽の光なのかも定かではない。
「っ! どこだ! 返事をしてくれ!」
名前さえ知らない君を呼ぶこともできずに、闇雲に叫ぶ僕は、どれほど滑稽だろう。
焦っても、どんなに必死に叫んでも、声はどこにも響かずに堕ちていく。
次第にチカラを失っていくカラダは重く、平地にでても、もう飛ぶチカラはない。
己の愚かさの代償を払うのは、いつも自分ではない。
知っていたはずなのに、驕っていた。
遠くにあったはずの陽の光が、不確かな世界にゆっくりと滲んでくる。
君の気配が見つからない。
絶望に満たされる僕は、存在が溶けるように薄れるのを感じた。
我、暁に消ゆを知る。
ゆっくりと失っていく意識の中で、僕は、君を求め闇に溶けていった。