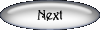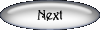我、妖怪に御座候
□午後6時_塀の前
1ページ/1ページ
鈴女さんが歪めた空間を抜けると、そこは路地だった。
コンクリートの塀が並ぶ細い路地。
直線的に伸びた道が、少し先で急に折れ曲がり見通せなくなる。
僕は、こういう場所は好きじゃない。
真っ直ぐに伸びた道と、同じに見える家が規則正しく並ぶような場所。
主様の想い人は、こんな所にお住まいでいらっしゃるのか。
「不服そうね。」
つないでいた手を放して楽しそうに腕組みした鈴女さんは、悪戯っぽく微笑んだ。
おかっぱ頭で淡い紅の小袖を可憐に着こなす姿は、どうみても大人しそうな女の子。
それでも、やっぱり妖らしく、僕が嫌がっているのがわかると楽しそうになる。
「いつもと雰囲気違いますよね?」
素直な感想が口から出てしまって、可愛い目に睨まれた。
「ははは。」
誤魔化し笑いで頭を掻いて、鈴女さんの目を逃れて背を向けた。
僕は正直すぎるらしい。
「この辺りにうちの主様の気配があるのですか?」
強引に話題を変えて、キョロキョロと周りを見わたし、目の前の塀の一つを指差した。
コンクリートの灰色の壁は、特に変わったところもない。
「この辺り。それしかわからないっ。」
強く言い切られて、まだ不機嫌なんだとわかった。
そのくせ、とても律儀なようで、
「鈴女さん、その、なんていうか、」
「黙ってっ。」
謝ろうとする僕を黙らせ、襟元で両手を合わせて気配をよむ。
真剣な表情で眉間にシワを寄せているから、僕は黙って結果を待った。
「なんか変。」
言いながら歩き出した鈴女さんについて行く。
空間を捻じって壁を抜け、また同じような路地に出て気配を探る。
それを繰り返す鈴女さんは、空間を越える程に眉間のシワを深くしてゆく。
「…おかしいわね。」
簡単にやっているように見えても、そうではないらしい。
薄っすらと汗が浮かぶ顔に、血の気はなくなっていた。
苦しいのか、呼吸をする度に肩が揺れる。
僕の主様なのに…。
なんの役にも立たず、鈴女さんに頼っているだけの自分が情けない。
「鈴女さん、少し休まれては?」
申し訳なさで顔が上げられなくて、下を向いたままそう言うと、すごいチカラで頭を叩かれてしゃがみこんだ。
くっ、痛っ!!
「うじうじするより先にやることがあるでしょ?! 悩むのは主を助けてからにしなさいよ!
…って、言ったよね?」
涙目の僕に鈴女さんは冷たく言い放つ。
コクコクと頷くと、大きなため息をついて僕に手を差し出した。
「ほんと、甘やかされてるんだから!!」
ため息まじりで僕を立たせ、つと僕の後ろの塀を顎でしゃくった。
「何ですか?」
振り返った塀に主様の匂いはない。
「そこ、変な感じ。」
ずっと眉を寄せたままの鈴女さんが、塀を睨んで腕を組み直す。
「…変な感じ。」
何の変哲もないコンクリートの塊を前に、僕も腕組みして鈴女さんが言う変な感じを探してみた。
一見、平らにみえる人工物の表面は、よく見るとザラザラでデコボコしてる。
野晒しになっているせいか所々にシミもある。
「このシミ、パンダに似てますね!」
嬉しい発見に声を踊らせると、またすごいチカラで頭を叩かれた。
…いっいだぃっ!
痛む頭を摩りながら、もう一度塀を見る。
ここに何かあるはずなんだ。
ぎゅっと眉を寄せ、見えない何かを探してシミを見つめた。
相変わらずパンダにしか見えないシミが、目に溜まった涙で歪む。
パンダじゃないなら、何なんだ。
パンダじゃなくて…、これがドアノブなら、ドアはこの一区切りのブロックになる。
小さくて、入れないよ…。
睨むうちにも目に溜まった涙が、映る像を歪めていく。
「…あたし、もう少しやってみるから。」
肩に置かれた冷たい手をつかみ、ハッとして鈴女さんを見た。
可愛らしい顔は蒼ざめ、色をなくした唇がかすかに震えている。
無関係の鈴女さんに、これ以上無理をさせちゃいけない。
『弱いモノは守れ。』
主様の数少ない名言が聞こえた気がした。
「僕が見つけます。鈴女さんは少し休んで。」
腰に括った瓢箪を外し、荒い息を繰り返す鈴女さんに手渡すと、鈴女さんは目を大きく見開いた。
「だって…。」
戸惑う鈴女さんの唇に人差し指をあて、にっこり笑う。
どうか、自信満々に見えますように。
「鈴女さんが休む間だけ、やらせてください。ね?」
この場合、鈴女さんが僕より『弱モノ』かは別として、僕にだってやれることがあるはず。
だって、僕は主様の優秀な従者なんだから。
僕のそんな気負いがどう伝わったのか、瓢箪を受け取った鈴女さんは、何故か赤くなって頬を膨らませた。
怒っちゃったかな?
心配になったけど、鈴女さんが黙ったままだから、また塀に向き直った。
パンダでも、ドアノブでもないなら…このシミはなんだ?
ああ、主様がここにいたなら、きっと僕を撫でてくださるのに…。
………。
手?
もしかして、主様の手の痕??
点々と塀に残るシミをじっと見る。
塀に手の痕?
見れば見る程、主様の手の痕にしか見えないソレに目を凝らして首を傾げた。
「鈴女さん、術に手で触ったら痕が残るんでしたっけ?」
「聞いたことないけど?」
「…ですよね?」
肩を竦めた鈴女さんに頷いて、やっぱり主様の手にしか見えないシミを指差した。
「ここが変です。」
「どこ?」
鈴女さんから瓢箪を受け取り、主様の手の痕の中心を示す。
「どんな風に?」
真剣な顔で塀を調べる鈴女さんは、そっとシミをなぞる。
「主様の手に見えるんです。」
「手?」
「気配とか、そういうのはわからないんですけど、なんか主様の手に見えちゃって。」
笑われてしまうかも知れない。
段々小さくなる僕の声は、最後には呟きになっていた。
「ん、ココね。」
確信に満ちた断言に驚いて顔を上げる。
「本当に?」
ニコリと笑った鈴女さんは、力強く頷いた。
「どんなチカラ使ったのよ? すごいじゃない?」
我、妖しき力を使役せり。
その名を主様への愛という。
鈴女さんに褒められて、僕は有頂天になった。
主様! 僕もついにやりました!
お役に立てましたよ!!
けど、世の中そんなに甘くない。
「じゃ、あたしの役目は終わったから。帰るね。」
あっさり言った鈴女さんに、「え?」と聞き返す間もなく。
「そこから入れるはずだから、後は頑張って!」
簡単な激励と共に、一瞬で消えた鈴女さんを引き止めることも出来なかった。
………。
主様、僕は…どうしたらいいんですか?!
『自分より強いモノは徹底的に利用しろ。』
主様のもう一つの格言が頭をよぎる。
今更遅いですよぉ、主様ぁ。
取り残された塀の前、僕はただただ呆然と立ち尽くした。