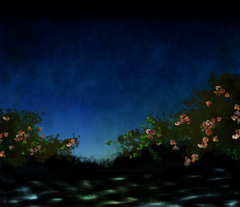
【今宵、君と紡ぐのは act.2】
分厚い雲が世界を薄明るい色に染めた、冬の終わりの夜。
連日の冷え込みが幾分か和らいだ今夜は、雨が止んだばかりで温い風が吹いている。
雨が降る度に春へと近づくせいか、湿った空気は晴れ渡った日のそれよりも生暖かい。
そう知ったのは、いつの頃だろうか。
「今日は暖かいですね」
「そうじゃのう」
コンクリートの上に、二人分の足音が響き渡る。
わしの横で絶妙な距離を取りつつ歩くのは、スーツの上からトレンチコートを羽織り、ストールを巻いたカミソリ先生。
互いの家がそれほど離れていないのと、二人共帰りが遅いこともあって、こうして一緒に夜道を歩くのも珍しくはなかった。
ただし、今夜はカミソリ先生がいつもより饒舌で。
「卒業式、無事に終わってよかったです。」
「ほんにな。」
カミソリ先生は当たり障りのない言葉を呟き、わしも適当な相槌を打つ。
普段はどんなに長い沈黙も厭わないのに、今夜に限ってよく話すのは、打ち上げで飲んでいた酒が原因なのだろう。
足取りはふらつくことなく、ひどく酔っているわけでもなさそうで、隙がないのは相変わらず。
内心そう思いながら、人気のない路地裏に差し掛かったところで立ち止まって問いかける。
「おんし、今日はどうした?」
「…はい?」
カミソリ先生もわしにつられて足を止め、その場には吐息だけが残った。
「今日はよく話しちゅう、酔いでもまわったんかと」
わしはサングラス越しにカミソリ先生の頬をまじまじと見つめたが、酒に酔った赤みは感じられない。
「酔ってませんよ。」
乾杯でビールを一杯飲んだだけですから、とカミソリ先生はどこかぎこちない笑みを浮かべる。
「…ほんならええが。」
わしが浅い溜め息をつき再び歩き出そうとした、そのとき。
「見ちゃいました。」
カミソリ先生はぽつりと呟いたきり、動こうとはしなかった。
「ん?」
俯き加減になったカミソリ先生の髪にそっと触れてみるが反応はなく、外見上は泣いているのか怒っているのかもわからない。
けれど何か苦しいことがあると、彼女の全身がそう訴えている気がした。
「何かあるなら、」
「坂本先生、告白されてましたよね。卒業式が終わってから数学準備室で。」
言葉を遮られたのは稀で、一瞬呆気にとられてしまう。
確かに今日は卒業式で、わしにも甘酸っぱい話が転がり込んだ。
カミソリ先生はその一部始終を見て、どうやら思うことがあったらしい。
「…最後まで言うてみ?」
わしはずり落ちてきたサングラスを直しながら、カミソリ先生を促した。
ふいに顔を上げたカミソリ先生は、淡々とした口調で俺に質問を投げかける。
「断ったのは、生徒だからですか?」
声の低さは、数学の問いを読み上げるときのもの。
カミソリ先生にとっては数学も色恋も大差ないのではないかと少々案じながらも、わしは答えた。
「…生徒かどうかは関係なく、ほいそれとあんな真摯な気持ちは受け取れん。」
相手の、卒業生となった女生徒はまさに真剣そのもので。
卒業まではと思いを隠し通したらしく、これからは生徒ではない、付き合ってほしいというようなことを言われた。
だが、わしの心はその声を聞くことはできても、受け入れる準備など何もしていない。
当然、やんわりと断った。
ハレの日に泣かせるものでもないだろうと気遣い、柔らかく丁寧に。
「叶わないこともある、それが人の道ぜよ。」
例えば、わしがカミソリ先生に対してどんな感情を抱いているか。
それをカミソリ先生が知らないのと同じくらい、わしもあの女生徒のことはわからないし理解するつもりもない。
そもそも思いの強さや深さは物差しでも測れないし、数値化することもできないのだ。
「でも…」
カミソリ先生は、こういうときに引くことを知らない。
納得いくまで貪欲に答えを求める。
「ほいなら、何だ?」
次の言葉を懸命に考える彼女の姿を見て、なんとなく察した。
今夜はアルコールが彼女の感情を引っぱり出している。
カミソリ先生の導火線のようなモンに火をつける方法を数秒で考え、わしは一つの単語を呟いた。
「軽蔑、か?」
「―っ、」
カミソリ先生はコートをぎゅっと掴み仁王立ちをしている。
全くもって、可愛げなどどこにもない。
「出来た大人ぶって、思いを流せるわしを軽蔑したか。」
それでもいい、
「違います、」
本心をさらけ出す相手としてわしを選んでくれたなら、
「違わん。おんしは、わしを軽蔑して妬んだ。大人の対応ができることを羨み恐れたんじゃろう。」
わしは何だって答える構えでいると、今ここで示すのみだ。
「わしは大人らしく振る舞ったつもりはない。わしの感情を押し通してしまった、子供と変わらん。」
カミソリ先生はすっかり黙ってしまい、わしはその手を片方掴んで引き寄せる。
抱きしめたりはせず、代わりに耳元で低く呟きながら。
「あの生徒がどれほどの思いを抱えていようと、わしには答えられん。それが現実じゃき。」
「…それは」
「ああいう痛みはいくつになっても辛い。わしも、」
そこまで言いかけて、ふいに気がつく。
この続きを言葉にしてはいけない。
いつも口にする愛情表現とは違うものになってしまう、と。
「坂本先生…?」
「…酔いがまわっちゅうのはわしじゃな。ほれ、早う帰らんと。」
わしはカミソリ先生の手を取ったまま、いつも通り歩き続ける。
後ろから訝しげな視線がちくちくとわしの頭に向かって投げかけられたが、あえて気づかないふりをした。
今はまだ、把握してはならない。
先の言葉を、逃げ場のない思いを、予想される結末を。
雲がふんわりと世界を包み込み、止んだはずの雨が一滴、二滴と再びコンクリートを湿らせ始める。
まるで誰かの心を代弁しているかのように。
早く帰る言い訳が一つできたと天を仰ぎながら、わしとカミソリ先生は家路を急いだ。
to be continued…